2013年04月
2013年04月23日
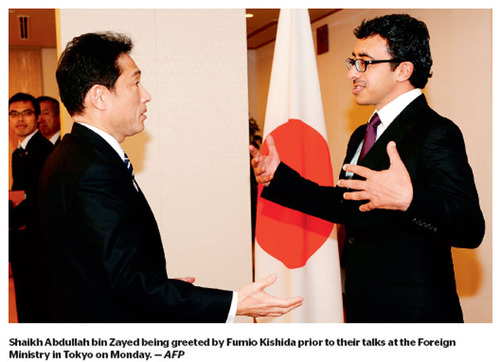
(サウジ)Juffali、仏Soitec社と太陽電池で合弁事業。
(韓国)中東プロジェクトなど安値受注で業績悪化の韓国建設業界。 **
*アブダッラー外相はアブダビ・ナヒヤーン家の王族。ハリーファ首長異母弟、ムハンマド皇太子実弟。
参考:ナヒヤーン家家系図およびUAE閣僚名簿
http://members3.jcom.home.ne.jp/maeda1/3-5-1aAbuDhabiZaidWifeSon.pdf
http://members3.jcom.home.ne.jp/maeda1/4-5-1UaeCabinet.pdf
**参考レポート「湾岸諸国でますます存在感を増す韓国企業」
http://members3.jcom.home.ne.jp/3632asdm/0244KoreaInGcc.pdf
2013.4.23
1979(昭和54)年、サウジアラビア現地に赴任
ここまで書いてきてアラビア石油の当時の状況を実際以上に楽観的に書いていることに自ら気がついた。会社生え抜きの先輩、創業時の苦労を知る人々からはお叱りを受けるかもしれない。楽観の根拠は多分転職に大いなる希望を抱いていた所為であり、或いはアラビア石油の居心地が悪くなかったということであろう。事実、中途入社の仲間で話し合うと異口同音に、以前の会社で社内外の厳しい競争に晒され給与もさほど良くなかったことに比べ、アラビア石油には競争と言えるほどのものは無く待遇も世間並み以上であると語り、転職組の意見は完全に一致していたのである。
入社後に配属されたのは現地事業所(会社では「アラビア鉱業所」と称していた)の予算を取りまとめる部署であった。仕事にも慣れた3年後の1979年、現地赴任の辞令が出た。採用面接の際、会社側からは現地赴任を前提としている旨を言い渡されており、来るべきものが来たということである。単身赴任するか家族を帯同するかは本人の選択にまかされ、赴任期間は単身3年以上、家族帯同5年以上とされた。
当時、日本企業の平均的な海外赴任期間は3~4年であり、5年はかなり長いが、筆者の場合は長女が6歳、次女が2歳の娘二人であり家族帯同の道を選んだ。海外赴任で大きな問題となるのは子女の教育、即ち日本語学校の有無である。英語圏なら将来のことを考え現地校に通わせ、週末は日本語補習校に行かせるという方法も考えられるが、サウジアラビアは公用語がアラビア語であり、カフジには外国人向けの小学校はない。そのためアラビア石油は東京都府中市にある明星(めいせい)学苑と契約し現地に幼稚園と小学校を開設していた。単独企業が企業内学校を持つケースは現代では例がなく、当時としても極めて珍しいケースであったが、家族とともに長期間赴任させるための会社の配慮だった。
仲間の送別会、親類縁者への挨拶等をすませ、1979年9月に前年開港したばかりの成田空港を出発、最寄りのクウェイト空港に到着したのは真夜中であった。機外に出るとまるでサウナに入ったような熱気に襲われた。人づてに聞いてはいたが湿潤で温暖な気候の日本から来た異邦人にとっては衝撃的な初体験であった。迎えの車に乗ってそのままカフジに向かう。カフジはサウジアラビアとクウェイトの中立地帯にある入り江の町であったが、その後1965年に両国政府により二分割されカフジはサウジアラビアの管轄下に置かれることになった。
カフジがサウジアラビア領になったことは会社と日本人社員にとって運命の分かれ道でもあった。カフジから最寄りの都会へはクウェイト中心街までが150KMでほぼ東京から静岡まで、サウジアラビア東部の都市ダンマンまでなら350KMもあり東京-京都間に相当する。いずれにしてもかなりの長距離であるが、クウェイトは比較的近く、しかもダンマンなどと比較にならない大都会である。そのため日本人は休日になるとクウェイトに出掛けることが多かった。しかし中間に国境ができたため入国審査、通関という面倒な手続きが必要になる。国際空港のように洗練されていないから国境の役人たちにはいつもイライラさせられた。それでも東京-京都間を日帰りドライブするよりはましである。
しかしサウジアラビア領で良かったことが一度だけあった。1990年のイラクのクウェイト侵攻と翌年の湾岸戦争の時である。もしカフジがクウェイト領であったなら、街はイラク軍に占領され自宅は彼らの略奪に晒されていたであろう。そして湾岸戦争では撤退するイラク軍がブルガン油田に火を放ったようにアラビア石油の施設も灰燼に帰していたかもしれない。アラビア石油の現場カフジがサウジアラビア領であったことは会社自身にとってある意味僥倖であったと言えなくはないのである。
1979年以前のカフジは政治的には無風状態であったが、その後はこの湾岸戦争を含めペルシャ湾周辺は戦乱が絶えなかった。赴任直後に始まったイラン・イラク戦争、その後の湾岸戦争、さらには2003年のイラク解放戦争と続き、その間にサウジアラビア国内ではイスラム過激派のテロが頻発している。勿論アラビア石油そのものも利権契約問題を抱えており、この問題で会社は苦悩し苦闘した訳である。
(続く)
本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。
前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町2-31-13-601
Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642
E-mail; maeda1@jcom.home.ne.jp
2013年04月21日
(バハレーン)英国TV放送の記者3名を追放。
(サウジ)ベテラン外国人女店員の強制解雇で小売店苦境。利益が3分の1以下に。
(オマーン)ガソリンなど燃料費補助の年間13億リアル。財政負担が深刻な問題に。
*Khalid王子は故Sultan皇太子・国防省の子息。新副大臣Fahd王子はサウド家外戚、Abdulaziz初代国王の弟Muhammad の孫。
2013年04月19日
2013.4.19
7姉妹(セブン・シスターズ)とOPECのはざまで
世界の石油の生産と価格は1970年代初めまでセブン・シスターズと呼ばれる7社の国際石油会社がほぼ独占していた。7社とはエクソン(旧エッソ)、モービル、シェブロン、テキサコ、ガルフの米国5社及びシェル(ロイヤル・ダッチ・シェル)、BP(British Petroleum)の英国2社のことである。このうちエクソン、モービル、シェブロンの3社はロックフェラーが創設したスタンダード・オイルが後に独占禁止法で分割されて誕生した会社でありルーツを同じくしている。その他の4社も米国と英国の企業でありアングロサクソン系と言うことになる。それゆえにこれら7社は「7姉妹(セブン・シスターズ)」と呼ばれたのである。
セブン・シスターズは結束が固く、石油価格の決定権は彼らが握っていた。これに最初に反抗したのがイランのモサデグ首相であり、彼は1951年にアングロ・イラニアン石油(BPの前身)を国有化した。しかしセブン・シスターズはイラン原油を国際市場から締め出し、このためモサデグはあえなく失脚した。余談であるがこの時セブン・シスターズの監視の目をくぐり抜け、タンカー「日章丸」をペルシャ湾に送り込み、イラン原油を買い付けて世界をあっと驚かせたのが出光興産である。ともあれイランの石油産業国有化は時期尚早であった。
その後石油価格が下落しセブン・シスターズが産油国からの買い入れ価格を一方的に引き下げた。これを契機に産油国は団結の必要性を痛感、1960年にOPEC(石油輸出国機構)を結成したのである。1966年の国連総会で、資源は本来所在国に帰する、とする決議がなされたことも追い風となり産油国で国有化の動きが加速した。1960年代はセブン・シスターズとOPECの力関係が逆転する潮目であった。産油国がその威力を見せ付けたのが1973年の第四次中東戦争であり、この時OAPEC(アラブ石油輸出国機構)は石油を武器として使う石油戦略を発動した。世に言う「オイル・ショック(第一次)」である。
1961年にサウジアラビアのカフジで本格的な石油生産を開始したアラビア石油は、まさにセブン・シスターズとサウジアラビアを盟主とするOPECが主導権争いを始めた時期に生まれたのである。そもそもアラビア石油がサウジアラビアとクウェイトの中立地帯沖合の利権を獲得できたのもそのような時代背景があったからと言える。当時既にサウジアラビアでは米国系セブン・シスターズ4社による現地操業会社アラムコ(Arabian American Company。略称ARAMCOは各単語の冒頭2文字ずつを結び合わせたもの)が石油の開発生産を行っており、クウェイトでは同じくセブン・シスターズのBPとガルフ石油が設立したクウェイト石油によって操業が行われていた。しかし両国の行政権が重なる中立地帯は石油利権の空白地帯だった。当時のサウジアラビアのサウド国王はこれを産油国が主導権を発揮するチャンスととらえ欧米以外の国に利権を与えることを検討、その結果アラビア石油が選ばれたという訳である。
中立地帯の利権が無名の日本企業に与えられたと知るやセブン・シスターズは露骨に嫌悪感を持ったと言われる。ソニーやトヨタなどの先端工業製品で欧米市場を席巻しつつあった日本に対する警戒心もあったであろう。また「石油開発のことなど日本人に解ってたまるか」という軽侮の気持ちがあったことも疑いない。このため現地で操業の立ち上げに携わった社員たちはアラムコの妨害行為を懸念した。しかし実際にアラムコに教えを請うと彼らは実に懇切丁寧に教えてくれたそうである。当時のアメリカ人は新参者に対しておおらかで度量が広かった。圧倒的な国力がもたらす余裕なのであろう。
一号井で巨大油田を掘り当てたアラビア石油はその後の開発生産操業も順調だった。筆者が現地に赴任したのはそのような1970年代の最後の年であった。
(続く)
本稿に関するコメント、ご意見をお聞かせください。
前田 高行 〒183-0027 東京都府中市本町2-31-13-601
Tel/Fax; 042-360-1284, 携帯; 090-9157-3642
E-mail; maeda1@jcom.home.ne.jp